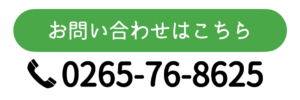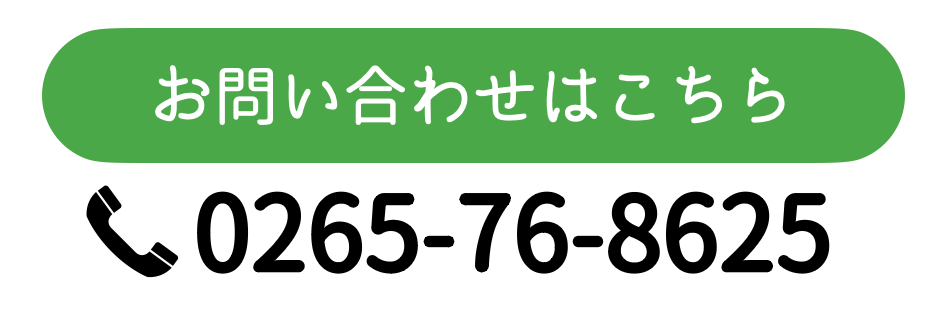犬が前足をあげている|考えられる原因と受診の目安を解説
「ソファーから飛び降りた後に前足をあげている」
「散歩から帰ってきたら前足をあげている」
このような様子がみられたら、どう対応すべきなのでしょうか?
愛犬が突然、前足をあげたり引きずったりしていると、不安になりますよね。
- すぐに動物病院に連れて行くべきなのか
- 何か処置をしたほうが良いのか
対応に迷うことも多いかと思います。
今回は、犬が前足をあげる原因と、ご家族の対応について解説していきます。
ご自宅でできる対策についてもご紹介しますので、ぜひ最後までお読みいただき、参考にしてみてください。
犬が前足をあげる原因
犬が前足をあげていても必ずしも異常とは限りませんが、急にあげるようになったり、ずっとあげていたりする場合には異常が疑われます。
ここでは、代表的な異常について解説していきます。
肉球や爪の異常
肉球や爪に異常があると、地面に足先を着ける際に痛みが生じるため、前足をあげることがあります。
主な原因は、
- 肉球にケガや炎症がある
- 指の間に炎症がある
- 爪が折れている
- 巻き爪がある
などです。
散歩時にガラスの破片や硬いものを踏むことで、肉球や指の間にケガや炎症が生じます。
また、皮膚炎により指の間を舐めることでも、炎症が生じます。
次のような爪の異常も、前足をあげる原因のひとつです。
- 爪が伸びすぎている
- 折れている
- 巻き爪がある
肉球や爪の異常では、常に足をあげるケースよりも、足をついたりあげたりするケースが多い傾向にあります。
骨折
「ソファーから飛び降りた後、前足をあげている」
「階段で転んだ後から前足をあげている」
といったように、高いところから降りた後や転んだ後に前足をあげている場合は、骨折をしている可能性があります。
骨折しやすいとされる犬種は、ポメラニアンやトイ・プードル、イタリアン・グレーハウンドなどの小型犬です。
また、高齢の犬では、骨の腫瘍により骨折することもあります。
骨折していると、足の腫れや変形、内出血もよくみられます。
骨折の多くは外科手術が必要になります。
脱臼
前足をあげているときは、脱臼も疑われます。
いつもと違う方向に前足が向いているときは、脱臼の可能性があります。
脱臼は、
- 関節に過剰な力が加わる
- 関節に変な方向から力が加わる
- 先天的に関節の構造に問題がある
といったことが原因で生じます。
脱臼をしていると、止まっているときも足をつけずに、常に前足をあげている傾向があります。
足に荷重をかけていそうに見えても、「足のつき方がおかしい」「少し浮かせている」といったことも特徴です。
関節炎
肩や肘、手首といった関節に炎症がある場合にも、前足をあげることがあります。
関節炎は高齢の犬や肥満の犬に多い病気です。
大型犬でよくみられますが、小型犬でも発症することがあります。
関節炎では、
- 走りたがらない
- 階段を上るのを躊躇する
といった症状がみられます。
関節炎は急に起こるのではなく、徐々に進行していく病気です。
日頃から愛犬の様子をよく観察し、変化にいち早く気づいてあげることが大切です。
神経学的な異常
前足をあげる原因のひとつに、神経学的な異常があります。
主な神経学的な異常として
- 頸椎の椎間板ヘルニア
- 脊髄梗塞
- 脳の異常
が挙げられます。
頸椎(首の骨)の椎間板ヘルニアとは、首の骨と骨の間にある椎間板が飛び出て、神経を圧迫する病気です。
神経が圧迫されるため、首の痛みや足の麻痺、歩行障害が生じます。
首に痛みがあると、
- 首がこわばる
- 上目遣いになる
- 動きたがらない
- 首を触ろうとすると怒る
- 抱き上げると鳴く
といった様子がみられます。
脊髄梗塞とは、脊髄に血液を送る血管が、何らかの原因で詰まってしまう病気です。
脊髄とは、背骨の中を通る神経です。
急に足が動かなくなることが特徴で、多くは片側に生じます。
ただし、脊髄梗塞では、あまり痛みはありません。
脳に炎症や腫瘍がある場合にも、前足をあげることがあります。
脳に異常があると、前足をあげる以外にも、よろけたり、手の甲を引きずったり(ナックリング)する症状がみられることがあります。
犬が前足をあげているときは動物病院に行くべき?
前足をあげているということは、前足に何かしらの違和感がある証拠です。
特に常に前足をあげている場合は、強い痛みが疑われますので、早めに受診しましょう。
異常の有無をみるために、前足の状態を確認したくなるかもしれません。
痛みにより怒る・嫌がることもあるので、無理に確認するのは避けましょう。
骨折や脱臼が疑われる場合も、包帯などで固定する必要はありません。
なるべく安静にし、悪化する前に動物病院を受診しましょう。
動物病院を受診する際は、下記に挙げるポイントを病院に伝えていただくと、診察がよりスムーズに進みますので、ぜひ参考にしてください。
犬が前足をあげているときに見てほしいポイント
一言で前足をあげているといっても、その症状は様々です。
ここでは、前足をあげるという症状をもっと掘り下げて、動物病院で症状を伝える際の参考にしてみてください。
いつ前足をあげている?
愛犬が前足をあげていたら、
- 足をずっとあげているのか
- 歩くときだけあげているのか
- 引きずるようにしているのか
など、前足をあげているタイミングをよく観察してみてください。
一番のおすすめは、動画を撮影することです。
愛犬が歩く様子を撮影し、診察の際に獣医師に見せてください。
動物病院では、緊張から歩いてくれないこともあるので、ご自宅での様子があると診断の大きなヒントになります。
痛みはありそう?
痛みがある場合は、体や足を触るときに嫌がったり怒ったりします。
患部を気にして舐めるといった様子も症状のひとつです。
強い痛みがある場合は、元気や食欲がなくなることもあります。
思い当たるきっかけがあるか
前足をあげる前に何かきっかけがなかったか、考えてみましょう。
きっかけとして多いものは
- 散歩から帰ってきた後
- 転んだ後
- ジャンプした後
などです。
小型犬の場合、段差がそこまでない場所でも骨折することがあります。
お家でできる対策
上記のような病気の予防や再発防止のために、お家でもできることがあります。
愛犬の足を守るためには、日頃からのケアが大切です。
爪切り
爪が伸びすぎると、折れたり、肉球に刺さったりします。
定期的に爪切りを行い、ケガを防ぎましょう。
ご自宅で切るのが難しい場合は、トリミングサロンや動物病院で切ってもらいましょう。
足裏の毛の手入れ
爪を切っていても足裏の毛が長いと、足を滑らせる原因になります。
足裏の毛も定期的にバリカンなどでカットしましょう。
カットする際は、指の間や肉球を傷つけないように気をつけてください。
肥満にさせない
肥満になると、足に負担がかかり、関節炎などが起こりやすくなります。
運動不足になると筋肉の量も減り、関節への負担も増します。
日頃から食事や運動に気をつけて、適正体重を維持するように心掛けましょう。
減量の方法がわからない場合は、動物病院に相談してみてください。
滑りにくい床にする
床がフローリングの場合、足が滑りやすく、ケガをしやすくなったり、足の負担が大きくなったりします。
カーペットやマットを敷く、ペット用のワックスを塗るといった対策をし、滑りにくくしましょう。
昇り降りの負担を減らす
ソファーやベッド、段差などの高さがあるところにステップやスロープを設置して、昇り降り時の負担を減らしてあげましょう。
ソファーを昇り降りがしやすいローソファーに替えるのも、ひとつの方法です。
特に高齢になってきたら、少しの段差でも関節への負担が大きくなるので効果的です。
最近、
「階段を上るのを嫌がるようになった」
「走るのを嫌がるようになった」
といった様子がみられたら、関節炎が疑われますので、獣医師に相談しましょう。
階段に入れない
階段は犬にとっては段差が高く、上り下りする際に足腰に負担がかかります。
急いで階段を駆け降りることも多く、ケガの恐れもあります。
ペットゲートなどを設置し、階段に入れないようにしましょう。
難しい場合は、抱っこで上り下りするとよいでしょう。
まとめ
前足をあげているとき、症状の判断をするのは困難です。
安易に「少し様子を見ても大丈夫だろう」などと自己判断せずに、動物病院を受診しましょう。
早めに受診することで、愛犬の痛みや苦痛を早く和らげることができます。
受診するかどうか悩む際は、ぜひお気軽に当院へご相談ください。
| 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜11:30 | ||||||||
| 17:00〜18:30 |