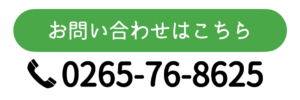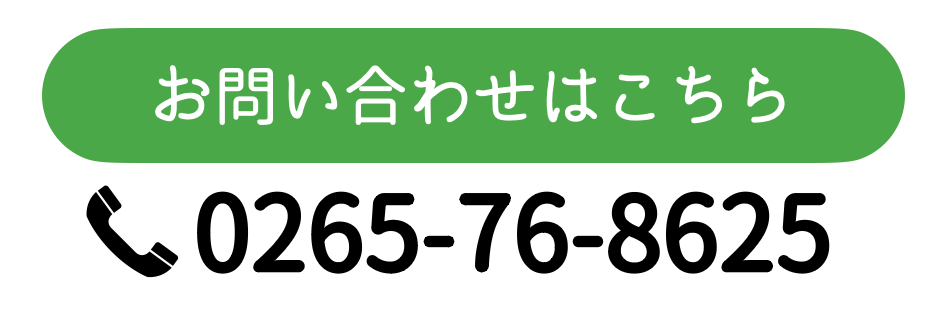犬のレッグペルテス病|小型犬で多い大腿骨頭壊死と骨頭切除について
レッグペルテス病という病気をご存知でしょうか。
まだ幼い小型犬が後肢を上げて歩いていたり、びっこを引くように歩くことがあればこの病気の可能性があります。
こんな症状が見られたら心配ですよね。
レッグペルテス病は放っておくと重度の歩行異常や強い痛みが生じることがあります。
今回はレッグペルテス病について解説します。
ぜひ最後までお読みいただき、レッグペルテス病についての理解を深めましょう。
レッグペルテス病とは
レッグペルテス病は無菌性大腿骨頭壊死症とも呼ばれます。
成長期の小型犬に多く発生し、大腿と骨盤の関節にある大腿骨頭という部分が壊死してしまう病気です。
ほとんどが左右どちらかの後肢に起こりますが、まれに両側に起こることもあります。
レッグペルテス病の原因
大腿骨頭が壊死してしまう原因は、なんらかの理由で大腿骨頭への血液の供給が途絶えてしまうことです。
なぜこのようなことが起こるのかは解明されていませんが、いくつかの説があります。
- ホルモンの影響
- 遺伝的要因
- 構造的な問題
などです。
レッグペルテス病になりやすい犬種は
- トイプードル
- ポメラニアン
- マルチーズ
などの小型犬です。
また、ほとんどが1歳未満の成長期に発症します。
レッグペルテス病の症状
最初は
「たまにスキップのような歩き方をするな。」
「後ろから見ると歩き方がおかしいな。」
という程度の異常から始まります。
病気が進行すると大腿骨頭の変形によって痛みが強くなります。
片足を挙げたままになったり、筋肉が萎縮して左右で足の太さに差が出たりします。
股関節周辺を触られることを嫌がったりすることもあるでしょう。
レッグペルテス病の診断
レッグペルテス病の診断は
- 視診
- 触診
- 画像診断
が有用です。
視診
犬を床で歩かせて歩き方の異常を診断します。
レッグペルテス病の犬はどちらかの後肢を庇うように歩いたり、びっこを引いたりします。
触診
レッグペルテス病の犬の股関節を触診すると痛がります。
特に股関節を後ろに伸ばした時に痛みを感じるのが特徴です。
また、痛い方の後肢を使わないように歩くので筋力が落ち、後肢の太さに差が出ます。
画像診断
レントゲンを撮ると
- 大腿骨頭の変形
- 大腿骨頭の虫食い像
- 大腿骨頭の骨膜の連続性の消失
などがわかります。
初期の段階ではこのような所見がみられないこともあります。
そのときは少し期間をあけてもう一度レントゲンを撮る必要があるかもしれません。
レッグペルテス病の治療
レッグペルテス病はほとんどの場合で手術が必要になります。
痛みを感じている時間が長ければ長いほど術後の回復に時間がかかるため、なるべく早く治療をしてあげることが大切です。
術式
壊死した大腿骨頭を取り除く手術を行います。
この手術を大腿骨頭切除術と言います。
大腿骨頭を切除すると痛みが軽減することが多いです。
「股関節の骨を取ってしまったら足がブラブラしてしまうのでは?」
と思う方もいるかもしれません。
股関節の周りには筋肉や腱などの結合組織が豊富です。
大腿骨頭を切除しても結合組織が股関節を支えてくれるので、術後も通常通り歩くことが可能です。
術後
手術直後から患肢を使うような運動を始めます。
小さな動きから始め、5〜10分かけて徐々に大きな動きにしていきます。
個体差はありますが、1ヶ月から半年もあれば正常に歩くことができるでしょう。
痛みを感じていた時間が長いと足を使うことへの恐怖心が強まって、正常に歩き出すまでに時間がかかることもあります。
また手術までに筋萎縮が進行しすぎていた場合も、回復の遅れがみられることがあります。
レッグペルテス病の予防法や注意点
レッグペルテス病の原因は遺伝や体質が関わるといわれているため、予防法はありません。
治療が遅れ症状が悪化すると痛みが強まったり、術後の回復が遅れたりするため早く治療をしてあげることが重要です。
日頃から犬をよく観察して異変があったらすぐに動物病院で診察を受けましょう。
まとめ
いかがでしたか?
レッグペルテス病は小型犬の子犬に多い病気です。
そして、早期発見と早期治療が大切です。
前述の好発犬種に当てはまる犬を飼っている方は是非この記事を参考にしていただき、歩き方に注目してみてください。
当院は外科手術の経験が豊富です。
もちろんレッグペルテス病の骨頭切除も対応可能です。
何かお困りのことがあればお気軽にご相談ください。
| 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜11:30 | ||||||||
| 17:00〜18:30 |