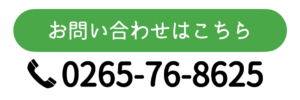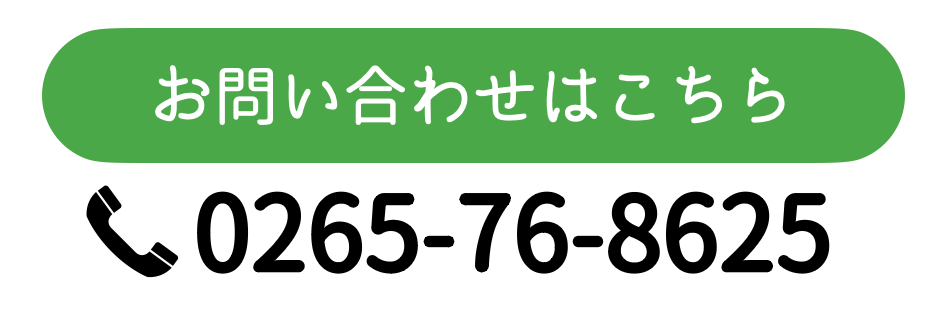犬の後ろ足に痛みがあるとどうなる? 犬の後肢に痛みがある時のサインや原因を解説
人間も年齢や病気、何気ない動作などさまざまな要因で足の痛みを感じることがありますよね。
足が痛いと活動や生活の質が低下します。
犬も同じように、特に後肢(後ろ足)に痛みが出ると、歩き方がぎこちなくなったり、お散歩を嫌がったりすることもあります。
犬は「足が痛い」と言葉で伝えることはできません。
だからこそ、日常の様子から痛みのサインを見逃さず、早期に気づいてあげることが大切です。
今回は、犬の後肢に痛みがあるときのサインや、考えられる原因、予防やケアについて解説していきます。
犬の後ろ足が痛いときのサイン
犬の後肢に痛みがあるときには、以下のような行動や姿勢の変化が見られます。
- 歩き方がぎこちない、後ろ足を引きずる
- 片足を浮かせて歩く・着地しない
- 立ち上がるのを嫌がる・ゆっくりしか動かない
- 階段や段差を避けるようになる
- お散歩を嫌がる・途中で座り込む
- 後肢をしきりに舐めたり噛んだりする
- 腰を触られるのを嫌がる
これらは、痛みや不快感のサインです。
特に急に現れた場合や、日に日に悪化している場合は早めの受診が必要です。
また、高齢犬では痛みが慢性化し、目立った症状が出にくいこともあります。
「最近あまり動きたがらないな」「寝てばかりいるな」と感じたときには、後肢の痛みや不調が隠れている可能性があります。

犬の後肢の痛みの原因
犬の後肢に痛みが出る原因で多いものとしては、次のような病気があります。
関節の病気(膝蓋骨脱臼、股関節形成不全、変形性関節症など)
小型犬では「膝蓋骨脱臼(パテラ)」が多く、膝のお皿が正常な位置から外れてしまうことで、痛みや歩行異常が出ます。
膝を伸ばす動きができなくなり、後ろ足をスキップするような歩き方になることがあります。
無症状の場合も多く、健康診断で偶発的に見つかるケースも多いです。
大型犬では、成長期に多い股関節形成不全や、加齢による変形性関節症もよくみられます。
いずれも関節がうまく機能せず、炎症や痛みを引き起こします。
これらの関節の病気は、徐々に進行していくケースが多いです。
体重の増加や運動の仕方によって悪化することもあるため、早期の診断と管理が大切になります。
靭帯の損傷(前十字靭帯断裂)
前十字靭帯とは膝関節に存在する靭帯です。
前十字靭帯が断裂すると、犬が突然足をつかなくなったり、立てなくなります。
多くの場合は加齢や変性した靭帯に負荷(散歩など日常的な動作)が加わることで、犬が立てなくなるといった症状が引き起こされます。
痛みが非常に強く、多くの場合で手術が必要とされます。
また、片方の前十字靭帯が断裂した場合、もう片方の前十字靭帯も数年以内に断裂することがあります。
最近では、前十字靭帯断裂と、肥満や内分泌疾患(糖尿病・クッシング症候群)との関連性も挙げられています。
予防には適正な体重や健康状態の管理も重要になります。
椎間板ヘルニア
椎間板ヘルニアは、脊椎にある椎間板というクッションが飛び出して、神経を圧迫してしまう病気です。
椎間板ヘルニアは軟骨異栄養犬種と言われる犬種で発症しやすいと言われています。
軟骨異栄養犬種とは
- ダックスフンド
- トイプードル
- シーズー
- フレンチブルドッグ
- ビーグル
などのことですね。
上記の犬種を飼われている方は、特に注意しましょう。
散歩や軽度の段差の上り下りのような日常動作でも、椎間板ヘルニアになることがあります。
椎間板ヘルニアの症状は神経の圧迫が軽度な場合と重度な場合で異なります。
神経の圧迫が軽度な場合の症状は腰の痛みです。
神経の圧迫が中〜重度な場合は、麻痺や立てなくなってしまうので、手術が必要になります。
神経症状(麻痺、排尿障害など)が長引くと、治療後も後遺症として残ってしまうことがあります。
神経症状が出ている場合は、早めに病院を受診するようにしましょう。
骨折
骨折は高所からの着地といった比較的大きなエネルギーが骨に加わることで起きます。
小型犬は骨が細いため、ソファーから飛び降りた際に骨折することがあります。
骨折は元気に走り回る若齢で見られることが多いです。
高いところに登らせないようにするなど、日々の生活に注意することで骨折のリスクを減らせます。
筋肉や腱の炎症・損傷
無理な運動や打撲、ジャンプの着地失敗などで筋肉や腱を傷めてしまうこともあります。
軽度であれば安静にすることで回復しますが、痛みが長引くときには検査が必要です。
骨の腫瘍
骨に腫瘍ができることで、痛みが出ることもあります。
犬の骨にできる腫瘍は、骨肉腫といった悪性腫瘍のことが多いです。
高齢犬で足の痛みが続く場合は、早めに病院に受診しましょう。

後肢の痛みに気づいたら動物病院へ
犬の後肢の痛みは、自然に治るものもあれば、進行して悪化してしまう病気もあります。
痛みが長引いている、歩き方がおかしいといった様子があれば、なるべく早めに動物病院を受診しましょう。
レントゲンや神経学的検査、必要に応じてCTやMRIなどの画像診断を行うことで、原因を特定し適切な治療を受けることができます。
特に体重の重い犬種や高齢犬は、関節や骨のトラブルを抱えやすいため注意が必要です。

おうちでできる予防とケア
犬の後肢の痛みを予防・軽減するために、飼い主様ができることをご紹介します。
体重管理
肥満は関節に大きな負担をかけ、膝や股関節の病気を悪化させます。
適正体重を保つことで、痛みの予防にもなります。
ご飯やおやつのあげすぎに注意し、定期的に体重をチェックしましょう。
適切な運動
運動不足も過度な運動も、足のトラブルの原因になります。
年齢や体力に応じて、無理のないお散歩や遊びを取り入れましょう。
ジャンプや激しい走り回りは、足腰に負担をかけることがあるため注意が必要です。
フローリング対策
滑りやすい床で生活していると、犬は足を踏ん張れず関節や腰を痛めてしまうことがあります。
マットやカーペットを敷くなどして、滑らない環境を整えてあげましょう。
定期健診・関節サプリメント
シニア期に入った犬には、定期的な健診で関節の状態をチェックしてもらうことをおすすめします。
また、関節の健康維持に役立つサプリメントを取り入れることも効果的です。
まとめ
犬の後肢の痛みは、関節・筋肉・神経・骨などさまざまな原因で起こります。
言葉で痛みを伝えられない犬だからこそ、歩き方や動きの変化に早く気付くことが大切です。
日頃からスキンシップをとり、足や腰に触れる習慣をつけておくことで、痛みのサインにも早く気づけるようになります。
当院では、犬の整形外科・神経疾患の診療にも対応しています。
「足をかばっているかも?」「歩き方が気になる」という場合は、お気軽にご相談ください。
| 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜11:30 | ||||||||
| 17:00〜18:30 |